�o�ώЉ�w���@��V��@�^�̂h�s�v���̐��ʂƂ�
�P�D�P�X�X�O�N��㔼����̂h�s�v���_
�@
(1)���R�}�[�X�̍s���ie�G�R�m�~�[�̏Ռ��j
�@�@�@�m2�̖@��
�@�@�@(a)�a�����b�A(b)�a�����a�A�ic�j�b�����b
�@���R�}�[�X�̍s���@�@�@�@�m2�̖@���F�m�E�i�m�|�P�j�^�Q
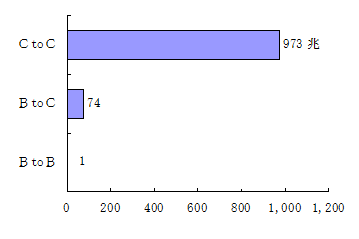
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Ɛ��F167���A���ѐ��F4411��
(2)�X�^���_�[�h�𐧂���ƃ^�_�ɂȂ�
�@�@�@�l�X�P�A�h�d�A�u���^�j�J�A�w���ρ[�ƁA�v���o�C�_�[
(3)�������͋N����̂�
�Q�D�h�s�v���͌ٗp�ɂǂ̂悤�ȉe���������炷�̂�
�@(1)�Z���̓}�C�i�X�A�������͂h�s�r�W�l�X�̑n�o�ɂ�����
�@(2)�z���C�g�J���[�̎d�����f�W�^���������
�@(3)�g�D�̓t���b�g������邪�A���ԊǗ��E�͕s�v�ɂȂ�̂�
�@�@�@�K�v�Ȃ̂͒������ł͂Ȃ��u�㔲���v
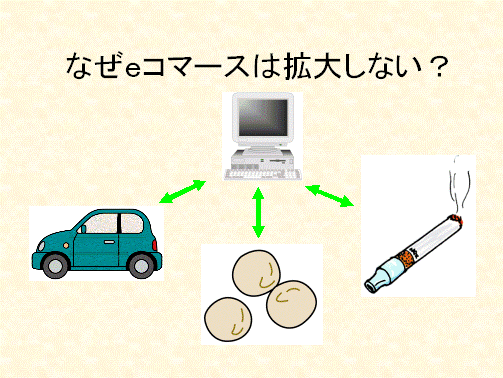
�Q�l�P�D�X�i��Y�w���{�o�ψÖق̋��d�ҁx2001.12.
�ꔪ���I�ɃC�M���X�Ŏn�܂����Y�Ɗv���́A�@�B�H�Ƃւ̎Y�ƋZ�p�]���ɂ���đ�ʐ��Y���\�Ƃ��A�H�Ɛ��i�̍L�͂ȕ��y�Ɠs�s�J���ҊK�����`�����邱�Ƃɂ���āA�����������v���I�ɕω��������B�_���Љ��H�ƎЉ�ւ̕ϖe�ł���B����Ɠ��l�̌��I�ω����A�C���^�[�l�b�g�𒆊j�Ƃ�����Z�p�̓o��ɂ���Ă����炳���ƌ���ꂽ�̂ł���B
�@�V�����v���I�Z�p�̓o��ɂ���āA���łɃA�����J�o�ς��ɉh������߂Ă���B������A����ɒǂ�����悤�ɓ��{�̌o�ύ\�������v���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�����̌o�ϕ]�_�Ƃ��p�w�҂̂����邾�����B
�@�������A�{���ɂh�s�͐V�������m�Ȃ̂��B�����ł͂Ȃ��B���Y�Ƃ����{�o�ς̌������ɂȂ�ƍŏ��Ɏw�E�����̂́A������O�Z�N�ȏ���O�̒ʎY�Ȃ̃r�W�����������B
�@�����̒ʏ��Y�Ɛ���̕������𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA�ʎY�Ȃ͈��Z�Z�N�����Z�N�����Ɂu�ʏ��Y�ƃr�W�����v�\���Ă���B����́u�Z�Z�N��ʏ��Y�Ɛ���r�W�����v�ł́A���{�̎Y�ƍ\�����ǂ̂悤�ɗU�����Ă����ׂ����ɂ��āA�����e�͐���Ɛ��Y���㏸��Ƃ�����̊���̗p�����B�����e�͐���Ƃ́A�����̏������������債�����ɁA���v�̐L�����傫���Y�Ƃ��琬���Ă������Ƃ�����ł���B�܂荑�����L���ɂȂ邱�Ƃɂ���āA�j�[�Y�����܂��Ă����Y�Ƃ�D��I�ɐU�����悤�Ƃ������v���̗v���ł���B����A���Y���㏸��Ƃ́A���Y���㏸�̉\�����傫���A���ۋ����̒��ŋ����D�ʐ����m�ۂł���Y�Ƃ��琬���Ă������Ƃ�����ł���B������͌����Ă݂�A�O�݂��҂���悤�ȋ����Y�Ƃ��琬���Ă������Ƃ����������̗v���ł���B���̓�̊���ɖ������Y�ƂƂ��āu�Z�Z�N��r�W�����v���I�̂��A����܂ł̌y�H�Ƃɑ���d���w�H�Ƃł������B�d���w�H�Ɖ��̎Y�Ɛ���͑傫�Ȑ��������߁A���{�o�ς͍��x�o�ϐ�����B������ƂƂ��ɁA���{�̎Y�Ƌ����͉͂��ď����ƌ�����ׁA����ɂ͈��Z�Z�N�ɂقǂ�ljƒ�ɕ��y���Ă��Ȃ������Ɠd���i���A�킸����Z�N�قǂōL���s���n��Ƃ����`�ō������������|�I�ɖL���ɂȂ����B
�@���̘Z�Z�N��r�W�����̑听���ɑ���������̒ʏ��Y�Ɛ���r�W�������A��㎵�Z�N�ɔ��\���ꂽ�u��㎵�Z�N��̒ʏ��Y�Ɛ���r�W�����v�ł������B���Z�N��r�W�����́A�Z�Z�N��r�W�������d�_���Y�Ƃ̑I���ɍ̗p���������e�͐���Ɛ��Y���㏸��Ƃ�����̊�ɁA����ɓ�̊��t�������Ă���B�ߖ��E����ƋΘJ���e��ł���B
�@�ߖ��E����́A�P�ɏȃX�y�[�X�A�Ȏ����A�ȃG�l���M�[����Q�̏��Ȃ��Y�ƂƂ��������ł͂Ȃ��A�ߖ�������̉��P�ɐϋɓI�Ɋ�^������Y�Ƃ𒆐S�ɂ��Ă������Ƃ�����ł���B
�@�ΘJ���e��̕��́A�H��̃��C���Œ��ڐ����Ɍg���悤�Ȃ���Ӗ��ŒP���ȓ����������A���S�ʼn��K�ŏ[�����̂���d����ł���Y�Ƃ�I�����悤�Ƃ�����ł���B
�@�d���w�H�Ɖ��̐����ŖL�����������������ʁA�ʏ��Y�Ɛ���r�W�����́A�o�ϐ����̂��߂̗v�������ł͂Ȃ��A������ΘJ�҂̐����b��ɂ܂œ��ݍ���ŁA�V���ȎY�ƍ\����͍������̂ł���B�r�W�����͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�u�d���w�H�Ɖ��̊�Ƃ��ꂽ�����e�͐������ѐ��Y���㏸����ɂ��Ă݂�ɁA�܁Z�N��A�Z�Z�N��̌o�ϊ��ɂ����ẮA�T���ė�������ݕ⊮�I�Ȃ�������I�ȊW�ɗ����Ă����B����ɑ��A��L�̎l�̊�ɂ��Ă݂�ɁA�e��̏[�����A���Ƃ��āA���݂Ƀg���[�h�E�I�t�W�ɗ����̂ƍl������B���������āA���Z�N��̎Y�ƍ\���r�W�����́A�����̊����A�P���ɁA�@�B�I�ɓ����o�������̂ł͂Ȃ��A���{�o�ς��߂���l�͂̏����⍑���̗~���̕ω��A���l�����Ɋւ���\���ȔF���Ɋ�Â��A��[���̗D��x�ɂ��Ă̔��f�������A�œK�r�W�������\�z���邱�Ƃ��K�v�Ƃ���悤�v�B
�@�l�̊�̔����ȃo�����X���ǂ�����Ă����悢�̂��A�T�d�Ɍ������Ȃ��ꂽ���ʁA���Z�N��r�W�������o���������́A�u�m���W�v�������B���m��蒆�S�̌o�ς���A�m�I�����̏W��x�������Y�Ƃ𒆊j�ɂ����o�ςւ̓]�����s���B���ꂾ���ł͂Ȃ��A�����Y�Ƃ̂Ȃ��ł��m���W��x�����߂Ă������Ƃ��]�܂����Ƃ��ꂽ�̂ł���B���t�Â��������Ⴄ���A����͌������Ă���u��v���̂��̂ł���B���̂��Ƃ́A�r�W�����ɋL�ڂ��ꂽ�m���W��Y�Ƃ̎�v�ތ^�Ɨތ^���Ɏ����ꂽ�����������҂����Y�Ƃ��݂�ƁA��w���炩�ɂȂ�B�����������A���Z�N��r�W���������p���悤�B
�@�m���W��Y�ƍ\���̒��j���Ȃ��m���W��Y�Ƃ́A��̓I�ɂ����Ȃ���̂ł��낤���B�܂��A�����̎Y�Ƃ́A�ݗ��^�̏d���w�H�Ƃɑ����āA���Z�N��̓��{�o�ς̔��W���\���Ɏ哱������ł��낤���B
�@��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA���i�K�ɂ����āA�����̒m���W��Y�Ƃ���̓I�ɗ\�f���邱�Ƃ͔�����ׂ��ł��邪�A���ʁA����ɂ��Ă̂�����x�̗\�����s�����Ƃ́A�m���W��^�Y�ƍ\���Ƃ����r�W�����̉ۂ��l���邽�߂ɂ��K�v�Ȏ菇�ƌ����悤�B
�@���̂悤�Ȋϓ_����A���i�K�ɂ������̗\���Ƃ��āA�m���W��Y�Ƃ̎�v�ȗތ^����ъe�ތ^���Ɏ��Z�N��ɂ����ē��ɍ������������҂�����Y�Ƃ�Ꭶ���Ă݂悤�B
�@�����J���W��Y��
�@���̎Y�Ƃ̊����ɂ����āA�����J������̔�d�����I�A�ʓI�ɑ�ł���A�����J���̐��ʂ����A���̎Y�Ƃ̔��W�ɂƂ��Č���I�Ȗ������ʂ����悤�ȎY�ƂƂ��āA���̏��Y�Ƃ��l���邱�Ƃ��ł���B
�@�d�q�v�Z�@�A�q��@�A�d�C�����ԁA�Y�ƃ��{�b�g�A���q�͊֘A�A�W�ω�H�A�t�@�C���E�P�~�J���A�V�K�������w�A�V�����A���ꓩ����A�C�m�J���ȂǁB
�A���x�g���Y��
�@���i�������̕��i���ނ̕��G�ȑg�ݍ��킹���琬�藧���Ă��邽�߁A���i�̐����ߒ��ɂ����āA���x�ȋZ�p����ыZ�\�Ɉˑ����邱�Ƃ��傫���Y�ƂƂ��ẮA���̂悤�ȏ��Y�Ƃ���������ł��낤�B
�@�ʐM�@�B�A�����@�B�A���l����H��@�B�A���Q�h�~�@��A�ƒ�p��^��[���A����@��A�H�Ɛ��Y�Z��A�����q�ɁA��^���@�B�A�����u�����h�ȂǁB
�B�t�@�b�V�����^�Y��
�@���i�ɑ��鍂�x�A���l�ȏ���҂̗~�����[�����邽�߂ɁA���̏��i�̊J���܂��͐����̉ߒ��ɂ����āA�f�U�C���A�l�āA�z�F���̑n�o������I�Ȗ������ʂ����悤�ȎY�ƂƂ��āA���̏��Y�Ƃ��l���邱�Ƃ��ł���B
�@�����ߗށA�����Ƌ�A�Z��p���x�i�A�d�C�������A�d�q�y��ȂǁB
�C�m���Y��
�@�o�ώЉ�S�ʂɂ����Đ����Ă���m���A���̌��p����ю��v�̑���ɉ����āA�m�����Y���A����Y�ƂƂ��āA���̏��Y�Ƃ��l���邱�Ƃ��ł���B
�@����T�[�r�X�A���T�[�r�X�A�r�f�I�Y�Ɠ�����֘A�A�\�t�g�E�F�A�A�V�X�e���G���W�j�A�����O�A�R���T���e�B���O�ȂǁB
�@�J��Ԃ��ɂȂ邪�A����͎O�Z�N�ȏ�O�ɏ����ꂽ���͂ł���B����ɂ�������炸�A��͎Y�ƂɁA�d�q�v�Z�@�A�d�C�����ԁA�Y�ƃ��{�b�g�A�W�ω�H�A�ʐM�@�B�A�����q�ɁA����T�[�r�X�A���T�[�r�X�A�\�t�g�E�F�A�A�V�X�e���G���W�j�A�����O�ȂǁA�h�s�v���̎�������łɎ�͎Y�ƂƂ��Ĉʒu�Â����Ă���̂��B���������Z�N��r�W�����ɂ́A�����̎Y�Ƃ͎��Z�N��ɍ��R�ƌ��ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�d���w�H�Ɖ��̐i�W�̉ߒ��ł��łɏo�����邢�͗������͂��߂��Y�Ƃł���Əq�ׂ��Ă���B
�@���������Z�N��r�W�����́A�����̎Y�Ƃւ̎Y�ƍ\���]���͊�{�I�Ɏs�ꌴ�������p���ׂ��ł��邱�ƁA�������V�K�Y�Ƃ̐����␊�ގY�Ƃ̓]���A��s�����ɂ�铮�ԓI�����z���̃v���Z�X�͎s�ꌴ�������ł͏\���ł͂Ȃ��̂ŁA�V�K�Y�Ǝx���⎑�{�E�J���̉~���ȓ]�����i�𐭕{���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���B
�@���̕��͂����ܐ��{�̕��ɂ��̂܂ܓ]�ڂ����Ƃ��Ă��A�����̐l�͉��̈�a���������Ȃ����낤�B�o�ϐ헪��c��h�s�헪��c���͂��߂Ƃ���o�ύ\�����v�h���咣�������Ƃ́A���łɎO�Z�N�O�̃r�W�����ɏ�����Ă����̂��B
�@�����ɁA���d�v�Ȃ��Ƃ́A�܂����x�o�ϐ����^������̓��{�ł��łɁu���͏�v�Ƃ����錾��ʎY�Ȃ����Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�@�������A���̈�㎵�Z�N��r�W���������܂��ܐ挩���ɗD��Ă��āA���̌��ʁA���Y�Ƃ���͎Y�ƂƂ��Ĉʒu�Â����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�@������㔪�Z�N��r�W�����ł́A�G�l���M�[����f�Ֆ��C�Ƃ������V���Ȑ������o�ꂷ��Ȃ��ŁA�@�G�l���M�[����̑ŊJ�A�A�����̎��I����y�ђn��Љ�̏[���A�B�Y�Ƃ̑n���I�m���W�̐��i�A�C������Z�p�v�V�ւ̒���A�Ƃ����l�̋Z�p�J���ۑ���f���Ă���B
�@���̂Ȃ��Łu�Y�Ƃ̑n���I�m���W�̋Z�p�J���v�ɂ��Ă͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B
�@�Y�Ƃ̒m���W�́A�Z�p�J���ɂ���Ďx������B�n�������͂������āA�����Y�Ƃ���w���x�����A�V���ȎY�ƕ�����J�邽�ߋZ�p�J���w�͂̐ςݏd�˂��v�������B
�@���Z�N��ɂ����ẮA�ȉ��̓�̕��������S�ƂȂ�B
(1)�V�X�e�����Z�p�ƃ\�t�g���Z�p
�@�킪���̎Y�ƋZ�p�́A�����̕���ł��Ȃ�̒��x���n�����i��ł�����̂́A����́A���l�ȋ@���v���Z�X�̑g�ݍ��킹�ɂ���ĐV�@�\��t�^����V�X�e�����Z�p�A�y�уn�[�h�E�F�A�ɁA���p�Z�p�A�f�U�C���A�T�[�r�X�Ƃ������\�t�g�E�F�A��̉����Ă����\�t�g���Z�p�̏d�v���͂���ɍ��܂��Ă����B
�@�V�X�e�����Z�p�ɂ��ẮA���݂̂悤�ɐ��Y���������剻���Ă���Ȃ��ł́A�X�̍H���̌������ƂƂ��ɁA�S�̂���̑傫�ȃV�X�e���Ƃ��Ĕc�����A���̌��������l���邱�Ƃ����߂��Ă���B�܂��A�ًƎ�Ԃ̘A�g�ɂ���Ă����炳���V�����V�X�e���̒a���́A����I�Ȍ����̌���ƁA�V�������i�A�T�[�r�X�̏o���𑣂��\�����傫���B
�@�\�t�g���Z�p�́A�}�C�N���R���s���[�^���@��A�v���Z�X�ɑg�ݍ��݁A�m�\�����邱�Ƃɑ�\�����B���k�r�h�̏o���́A�R�X�g�̒ጸ�A���^����ʂ��ă}�C�N���R���s���[�^�̗��p����w�e�Ղɂ���B�}�C�N���R���s���[�^�Y�v���Z�X�ɉ��p���邱�Ƃɂ��A�Z���T�[�Z�p�̐i���Ƃ����킹�ĎY�Ɨp���{�b�g���m�\������A���l���H��̎������\�ƂȂ�B����ɂ��A�@���i�폭�ʐ��Y�A�A�Ȏ����A�ȃG�l���M�[���A�B�i���̋ώ����A�C�J�����̉��P�Ȃǂ������炳���B�܂��A�@��ւ̉��p�ɂ��A�@�\�̑��l���A���x�����\�ɂȂ�B
�@�\�t�g���Z�p�ƃV�X�e�����Z�p�͂��ꂼ��P�Ƃɔ��W������̂ł͂Ȃ��A���҂����ݕ⊮�I�ɔ��W���Ă������̂ƍl������B
(2)�V���ȉȊw�m���Ɋ�Â��Z�p
�@�A�����t�@�X�ޗ��A���t�@�C�o�[�A�j���[�Z���~�b�N�X�A���@�\�������A�����ޗ��A�Ɍ��ޗ��Ȃǂ̐V�ޗ�
�A���[�U�[���p�Z�p
�B���k�r�h�A�Z���T�[
�C�p�^�[���F���A�l�H�m�\�Ȃǂ̍��x�ȃ\�t�g�E�F�A
�Ƃ������Z�p�̊J�����K�v�ł���B
�@�}�C�N���R���s���[�^�⒴�k�r�h�Ƃ������t���o�ꂵ�Ă��邱�Ƃ�����̗���f���Ă��邪�A�����Ă��邱�Ƃ͎��Z�N��r�W�����Ƃ܂����������ł���B��̋Z�p�́A�V�X�e�����Z�p�ƃ\�t�g���Z�p�Ƃ�����ɕ������Ă��邪�A���̓�̋Z�p���܂Ƃ߂��̂����݂̂h�s�i���Z�p�j�ł���B
�@�������������I�Ȍ�������ƐV�������i�E�T�[�r�X�̏o���𑣂��Ƃ��Ă���_���A���̂h�s�v���_�Ƃ܂������������B�����āA���ꂪ�������Z�N���O�ɏ����ꂽ���͂Ȃ̂ł���B
�@���łȂ̂ŁA��Z�N��r�W�����ŏ���ǂ̂悤�Ɏ��グ���Ă���̂����݂Ă݂悤�B�@��Z�N��r�W�����̎傽��e�[�}�́A�o�ϐ����������̂ɐ����̖L�������������Ȃ��Ƃ����u�L�����̃p���h�N�X�v�������ɉ������Ƃ������Ƃ������B��Z�N��r�W�����́A���_�̂Ȃ��́u��̐��i�v�Ƒ肵���Ƃ���Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@��Z�N��́A��̋}���Ȑi�W�������܂�A���O�Ƃ��ɍL�͂ȕ���ɂ����Ċv�V�I�ȉe���������炷���ƂɂȂ낤�B
�@��́A���������̌���A�J�����Ԃ̒Z�k��J�����̉��P�A�n��̐U���A��������S�ۏ�A����ɂ͋���╶���̕ϊv���X�ɉ����A�V���ȍ��E�T�[�r�X�̒A���Y�����E��ƊԎ���̍�������V�����Y�ƕ���̊J��Ƃ������Y�Ɗ����̖ʂłƂ�킯�傫�ȕω��������炷�ƌ�����B
�@��́A����ƒʐM�̂��ꂼ��̕���ł̋Z�p�i�������݂ɍ�p���Ȃ���Z�����Ă������Ŕ��W������̂ł���B�Ɠ����ɁA�o�ώЉ�̃j�[�Y�Ƒ��݂ɍ�p���Ȃ��犈�͂ɕx�ޏ�����W���Ă������̂ł���B
�@���̂悤�ȏ�̐i�W�̂��߂ɂ́A���l�b�g���[�N�ƃf�[�^�x�[�X�ɑ�\�����A��������C���t���X�g���N�`���̐�s�I�������s���ł���B���C���t���X�g���N�`���͋�Z�N�ォ���ꐢ�I�ɂ����Ă̌o�ώЉ�̊�b���Ȃ����̂ł���B�܂��A����ƕ����āA���ݖ������̏ɂ���d�q�����̃��[�����̃\�t�g�ȃC���t���X�g���N�`���������d�v�ł���B
�@�����Ɠ����ɏd�v�ȉۑ�́A���C���t���X�g���N�`���̎��̌���̂��߂̕s�f�̌����J���Ƃ�����g�����Ȃ����߂̎Љ�S�̂̏�Ή��\�͂̑��i�ł���B���̂��߂ɂ́A�l�ɂƂ��Ďg���₷���A�S�̂Ɏ�����₷�����Z�p�E���V�X�e���ɂ��ăn�[�h�E�\�t�g�̗��ʂ���Z�p�J���Ɏ��g�݁A���̕��y�ɓw�߂�ƂƂ��ɁA��K�́A���G�ȃ\�t�g�E�F�A�̊J���͂̋����Ɏ�������T�[�r�X�Y�Ƃ̍��x����l�ނ̈琬�A����ɂ́A�Љ�S�̂ɂ킽������E�P���������I�ȑ���u���邱�Ƃ��d�v�ł���B
�@�܂��A����܂ł̏���́A�_���I�E�����I������x�[�X�Ƃ��Ă��邽�߁A�����ł��邪�A�_��Ɍ�����Ƃ������炢������A�l�Ԃ̂悤�ȑ��푽�l�ȏ�����ɂ��������I���f�͍���ł������B��ꐢ�I�Ɍ����āA�^�̏�Љ�̎����̂��߂ɂ́A����܂ł̏���Z�p��⊮����A���l�Ԃɋ߂�����Z�p�̎��������҂����B
�@�����́A���肵��Ȃ��v���X�Ɠ����ɁA�Ή������Ə��Ȃ���ʃ}�C�i�X�ފ댯��������B������ݏo���n��ԁA�Ǝ�ԁA�K�͊ԓ��̐V���Ȋi����v���C�o�V�[�̕ی�A�Z�L�����e�B��e�N�m�X�g���X�̑��哙����L�̖��ɂ��čl������K�v������B
�@�Ȃ��A�䂪���̏ꍇ�A�ȐS�`�S�Ƃ������t�ɏے������悤�ɁA�����A�L���ɂ̂�Ȃ��R�~���j�P�[�V�����ԃ����^���e�B�[������A���ꂪ��̏�Q�ƂȂ�Ȃ��悤���ӂ���K�v�����邾�낤�B
�@�����Ă��邱�Ǝ��͎̂��Z�N��r�W�����A���Z�N��r�W�����傫���ς��Ȃ����A�l�b�g���[�N��d�q����Ƃ������t���o�Ă��Ă��āA���܂̂h�s�v���_�Ɉ�w�߂Â��Ă���B
�@���̕��͂́u��v�Ƃ������t���u�h�s�v���v�ɒu�������邾���ŁA���̕��͂��h�s�헪��c�̕����ƌ��������Ă��A�����̐l�������M���Ă��܂����낤�B����قǁA���܂̂h�s�v�����_�́A��Z�N�O�̒ʎY�r�W�������甲���o���Ă��Ȃ��̂ł���B�ƌ������A��̗���Ƃ����̂͂��̎O�Z�N�ԁA��т��đ����Ă���g�����h���Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�@���ꂾ���ł͂Ȃ��B���̂h�s�Ɠ����悤�ɁA��͍��܂ʼn��x���u�[�����N�����Ă���B�Ⴆ�Έ�㔪�Z�N��O���A�}�C�N���G���N�g���j�N�X�v���Ƃ������t�����E�����삯�������B�n�d�b�c��h�k�n�ŁA�}�C�N���G���N�g���j�N�X�̌ٗp�ɗ^����e�����c�_����A���{�ł͈�㔪��N�ɐ��J�g�ƗL���҂��������ٗp��萭���c���u�l�d���Ή��܌����v���܂Ƃ߂��B
�@�܂��A���{�̘J���Ȃ���㔪�l�N�Ɂu�Z�p�v�V�ƘJ���̎��ԁi�l�d�ҁj�v�A���N�ɂ́u�Z�p�v�V�ƘJ���̎��ԁi�n�`�ҁj�v�Ƃ�����r�I�傪����Ȓ������Ƃ�܂Ƃ߂Ă���B
�@�����̃}�C�N���G���N�g���j�N�X�v���́A�e�`�i�t�@�N�g���[�I�[�g���[�V�����j���Ƃn�`���i�I�t�B�X�I�[�g���[�V�����j�Ƃ�����̗v�f�ō\������Ă������A�ŏ��ɖ��ɂȂ����̂��e�`���̉e���������B�H��ɂm�b�H��@�B��Y�Ɨp���{�b�g�Ƃ������Z�p�����p�������Y���{������ɓ������ꂽ���ƂŁA���m���̌��ꂩ��l�������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ɛ^���ɐS�z���ꂽ�̂ł���B
�@����܂ł��l�X�Ȏ������Z�p�����݂������A�e�`�@��͋Z�\�J���҂��ւ��Ă����m�b��I�̋Z�܂ő�ւ��Ă��܂��B�m�b�H��@�B��Y�Ɨp���{�b�g�͑��삳���o���Ă��܂��A��N�ڂ̃I�y���[�^�ł��o�����\�N�̃x�e�����ƑS�������i���̐��i�����邱�Ƃ��ł���̂��B������ꕔ�̌���J���҂͔������A�܂�Ń��b�_�C�g�^���̂悤�ɂe�`�@�킪���҂ɂȂ������Ƃ��������B�������A��������̏ȗ͉��̐i�W�������I�Ȑ��Y���㏸�������炵�A�}�[�P�b�g�̔����I�ȏ㏸�������炷�Ɨ\�������l�������B
�@����ł́A���ۂɉ����N�������̂��B�����Ƃ̏A�ƎҐ����S�̂ɐ�߂�䗦�́A�e�`�@�킪����ɓ������ꂽ��㔪�Z�N���ʂ��āA�قƂ�Ǖω����Ȃ������̂ł���B����Z�N��ɂ͂����Ă��̔䗦�͉������Ă��Ă��邪�A����͒����Ȃǂɐ��Y���_���ړ]���Ă������̉e�������ꂽ���߂ŁA�e�`���̉e���ł͂Ȃ��B
�@����A���Z�N��㔼�ɂ́A�}�C�N���G���N�g���j�N�X�v���͂n�`�i�I�t�B�X�I�[�g���[�V�����j���ɍL�����Ă������B�p�\�R����I�t�R���i�I�t�B�X�R���s���[�^�j�������J���҂̎d����D���̂ł͂Ȃ����ƍl����ꂽ�̂ł���B
�@�����œ����悤�Ɂu�J���͒����v�ŁA�����E�̏A�ƎҐ����ǂ̂悤�ɕω����Ă����̂����Ă݂悤�B������͍ŋ߂ɂȂ�܂ŁA��т��Ď����A�Ǝ҂̍\����͍��܂葱���Ă���B�p�\�R���͑S�̂Ƃ��Ă݂�Ύ����J���҂̎d����D��Ȃ������̂ł���B
�@���̂悤�ɁA�}�C�N���G���N�g���j�N�X�v���́A�m���ɐ��̒��ɕω��������N���������A����͉ߋ����炸���Ƒ����Ă����ω����p�������邾���ŁA�����Ċv���̖��ɒl�����A���̕ω��������N��������ł͂Ȃ������̂ł���B
�@����Ȃ̂ɁA����܂Łu��v�͉��x���u�[�������o���Ă����B�Ⴆ�Δ��Z�N��㔼�̂u�`�m�i�t�����l�ʐM�ԁj�̃u�[���ł���B�����X�ɐ�p�[����ݒu���A�ǂ̏��i���ǂ�Ȏ��ԑтɂǂꂾ�����ꂽ�̂��A�l�X�Ȕ̔���ʐM�������āA���A���[�J�[�ւƖ���������B���̃f�[�^�Ɋ�Â��Ď����������s���邩��A�����X�ɂƂ��Ă͔�����ɊǗ��̎�Ԃ��Ȃ��邵�A���ɂƂ��Ă͍ɂ̈��k���\�ɂȂ�B���[�J�[�ɂƂ��Ă����X�ƕς����v�̕ω�����Ɏ��悤�ɕ����邩��A�v��I�Ŗ��ʂ̂Ȃ����Y���\�ɂȂ�Ƃ����d�|�����B���̃V�X�e���ōł��L���ɂȂ����̂���㔪��N�ɂo�n�r�V�X�e���������Z�u���C���u���ł���B
�@�܂��A���[�J�[�̑�����݂Ă��A�g���^�͔��Z�N�㔼�ɂ́A�J���o�������̓d�q�����������Ă���B�J���o�������́A�ŏI�I�ȎԎ�ʐ��Y�ʂɕK�v�ȕ��i��K�v�ȃ^�C�~���O�ŁA�K�v�ȗʂ������B���Ă������Y�����ł���B��������ς���A���i�ɂ��������ɁA���ꂽ���������Y����Ƃ����������B�g���^�́A���Ƃ��Ɛ��Y�ԂɃJ���o�������čs���Ă������̂��A�R���s���[�^�ɂ�鎩���V�X�e���ɒu�������A��㔪��N�ɂ̓r�W�l�X���f�������̐\�����n�߂Ă���B
�@���̂悢���Ȃ炨�C�Â��Ǝv�����A�h�s�v���̖{���Ƃ��Č��`����Ă���T�v���C�`�F�[���E�}�l�W�����g�́A���̂u�`�m���̂��̂Ȃ̂ł���B
�@�u�`�m�ɂ����V�X�e���́A�W���X�g�C���^�C���Ƃ����āA���i���H��Ŏg�p���钼�O�ɔ[����������A�̔����鏤�i�𑽕p�x���ʔz�B������K�v�����邽�߁A�z���g���b�N�̔r�C�K�X�ɂ�����肪�w�E���ꂽ��A���i�H��Ɏ��̂��������ꍇ�ɕ��i�̋����ꂩ�琶�Y�V�X�e���S�̂��X�g�b�v���Ă��܂����X�N���w�E���ꂽ�肵�����A�ɃR�X�g�̍팸���ʂ͑傫���A����Ƃ̂������ɂ͕��y���čs�����B
�@�������u�`�m���قƂ�ǂ̏����X�ɕ��y���čs�������Ƃ����ƁA�����Ă����ł͂Ȃ������B���[�J�[�ɂ��n��x�z�̋����Ƃ�����K�͂ȏ����X�������u�`�m�̑ΏۂƂȂ����̂ł���B���̗��R�͂�͂�R�X�g�ł������B
�@�o�ώY�ƏȂ́u���Ɠ��v�\�v�i�������N�j�ɂ��ƁA�]�ƈ��ܐl�ȏ�̏����Ƃ̓X�ܐ��͑S�̂̓�こ�����A��������z�̔����߂Ă���B�܂�A�O���̑�菬���X�����ʐM�ԂɑՂ��Ă����A�̔��z�̔������J�o�[���邱�Ƃ��ł���̂�����A����[�J�[�ɂƂ��ď\�����������A���ꂪ�R�X�g���l�����Ƃ��̕��y�̌��E�������̂ł���B
�@�h�s�v���Ńp�\�R���������I�ɕ��y���A�C���^�[�l�b�g�o�R�̐ڑ��ŒʐM�������ጸ���邱�Ƃɂ���āA���̂u�`�m���n��g�����z���A������X���܂߂Ċg�債�čs���\�����łĂ���A���ꂪ�T�v���C�E�`�F�[���}�l�W�����g���B��u�`�m�ƈقȂ�_�ł���B
�@���������ӂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���łɏ\���ȃ����b�g�������܂�镪��ł͂u�`�m�̓������I����Ă��邽�߁A����T�v���C�`�F�[���E�}�l�W�����g�̕��y�ŃJ�o�[�����̂́A���͑��������v���̒Ⴂ�Ƃ������ŁA���[�J�[�≵�ɂƂ��Ď�Ԃ��肩�����āA�ׂ��̔����Ƃ������ɂȂ�Ƃ������ƂȂ̂ł���B
���s�ɏI������r�h�r
�@�u�`�m����ƊԃV�X�e���̃G�[�X�ł������Ƃ�����A��㔪�Z�N��㔼�̊�Ɠ��V�X�e���̃G�[�X�́A�헪�I���V�X�e���i�r�h�r�j�̍\�z�ł������B��㎵�Z�N��̏��V�X�e���́A�{���ɐ��Y������̗��t���̂�����̂���ł������B�Ⴆ��s�̏��V�X�e�����l����ƕ�����₷����������Ȃ��B
�@��s�ɃL���b�V���f�B�X�y���T�[��`�s�l�����y����O�́A��s�ɗa���ʒ��Ƃ͂������ďo�|���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���ꂪ�L���b�V���J�[�h�ꖇ�����čs���ǂ̎x�X�ł��ȒP�ɓ��o�����ł���悤�ɂȂ����B
�@���p�҂��֗��ɂȂ����Ɠ����ɁA����͋�s�ɂƂ��Ă��傫�Ȑ��Y���̌����ɂȂ������B�Ȃɂ���A���܂܂łǂ�ȏ����̌ڋq�ł��������������ő�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��A�����̌ڋq�͊�{�I�ɋ@�B����������Ă����悤�ɂȂ�������ł���B���̂��ߑ����ŎD��������Ă���悤�ȍs���͑啝�ɍ팸���ꂽ�̂ł���B
�@����������s�̊���n�V�X�e���ɑ�\�����u��������v�V�X�e�����́A��{�I�ɂ͈�㎵�Z�N��ł��̊�Ղ𐮂����Ƃ����Ă悢�B
�������A�����ŃV�X�e���J���͏I�����Ȃ������B�u����܂ł̂悤�ȒP���Ȍv�Z��W�v�Ƃ������P���v�Z���R���s���[�^�֒u��������̂ł͂Ȃ��A�����ƌo�c�헪�ɕK�v�ȏ��������V�X�e���A���邢�͐V�����}�[�P�b�g�J��Ɏ�����悤�ȏ��V�X�e���̍\�z���K�v�ł���n�Ƃ���̂��헪�I���V�X�e���̍l�����������B��s�̃V�X�e���ł���A���Z�s��̏��A�ڋq���A����ɂ͍s���̐l�����܂œ����Ǘ����A�o�c���f�̎x���Ǝ��������{�I�Ɍ��������悤�Ƃ����̂��A���̖ړI�������B
�@�����A�����̊�Ƃł��̎��g�݂͎��s�����B�Ȃ��Ȃ�A���ł�����ł����V�X�e���ɍڂ�����܂��s���Ƃ����̂͌��z����������ł���B
�@�Ⴆ�ΐl���������ׂăR���s���[�^�̃f�[�^�x�[�X�ɓ���āA�K�ޓK���̐l�����߂����������悤�Ƃ���V�X�e�����������B�������A�����̐l���ٓ��͗����ǂ���ɂ͂����Ȃ��B�Ƒ��̎���łǂ����Ă��]�ł��Ȃ��l��������A���낢��ȋ��牡������������ŁA�����̐l���ٓ��̓h���h���̐킢�ɂȂ��Ă��܂��̂��B���ǁA���������l���V�X�e�����g����̂́A���߂��v�����g����Ƃ��̒P�Ȃ郏�[�v���E�t�H�[�}�b�g�ɉ߂��Ȃ��Ȃ����肷��̂ł���B
�@�}�[�P�e�B���O�̂��߂̃V�X�e�����������B������ڍׂɌڋq���͂����Ƃ���ŁA���ꂩ�甄��鏤�i���\���ł���킯�ł͂Ȃ����A�܂��Ă�V���i�̃A�C�f�A�����܂��킯�ł͂Ȃ��B���ǃf�[�^���͂╪�͂̎�Ԃ��肩�����āA���琶�Y������Ɍ��ѕt���Ȃ����V�X�e������ʐ��Y�����悤�ɂȂ����Ƃ����̂��A��㔪�Z�N��̓����������̂ł���B
�u�������v�͋N����̂�
�@ �h�s�v���_�҂������A���R�}�[�X�̍ő�̌��ʂƂ��Ă�����̂��A�u�������v���ʂł���B�C���^�[�l�b�g�Ŏ�����s���A���E���̏���҂����[�J�[�ƃ_�C���N�g�Ɍ����B�������A���͑����ɓ`�B����A����R�X�g���[��������A����܂ł̂悤�ɉ����Ǝ҂⏬���Ǝ҂̎��ʂ������͂邩�Ɍ����I�Ȏ�����\�ɂȂ�B���������āA����܂ʼnE���獶�ɏ��i�𗬂������ō�����V�Ă��������⏬���Ƃ̓C���^�[�l�b�g�ɂ��̍���D���A���̒��̎���̎嗬�h�̓l�b�g�Ɉڂ�A�Ƃ����̂��T�^�I�Ȓ������_�ł���B
�@���̖\�͓I�ȋc�_�́A���̒��̎x�������Ȃ�Ă���悤�ŁA���{�̊����s��ł͂��Ȃ�̐������Ǝ��v�����ւ鉵����ƂɐM�����Ȃ��悤�Ȉ��������������Ă���B
�@�������A�l�b�g�����y���Ă������Ƃ����ނ���Ƃ������Ƃ́A��ʓI�ɂ͂Ȃ��̂ł���B����́A���ʂ͂��Ȃ炸���̔w��ɕ������Ă��邩��ł���B
�@�Ⴆ�X�[�p�[�}�[�P�b�g�Ńg�C���b�g�y�[�n�[���㔪�~�Ŕ����Ƃ���B������l�b�g����Ń��[�J�[���璼�ڔ������Ƃ��ł����Ƃ��悤�B���[�J�[�ł͂��̏��i����㔪�~�ŏo�ׂ��Ă����Ƃ���B����҂��l�b�g�����ŁA���̏��i���Ƃǂ��Ȃ邩�B�g�C���b�g�y�[�p�[���͈̂�㔪�~�ł��A�������܁Z�Z�~���Z�Z�Z�~���������āA���ǂ��̂����������g�C���b�g�y�[�p�[��Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ȃ�̂��B
�@�������珬���X�����ꂼ�ꃁ�[�J�[�Ƀl�b�g�����������悢�B��������A�����Ǝ҂̃}�[�W���������ł������Ȃ�͂����A�Ǝv���邩������Ȃ��B�������A������ʖڂȂ̂ł���B���̗��R�͎O����B
�@���͕����R�X�g�̖��ł���B���m���^�ԂƂ��̉^���Ƃ����̂́A�����������Ȃ�A�L���O���������肢����Ƃ������A�A������肢����Ƃ����`�Ō��܂�B��Z�Z�O�����̂��̂���^�Ԃ̂��A�S�܂Ƃ߂ĉ^�Ԃ̂��قƂ�ǃR�X�g�͕ς��Ȃ��̂��B
�@����P�������邽�߂ɁA���[�J�[���֓��Ɉ�ЁA�����X����B�ɕS�Б��݂����Ƃ��悤�B���������X���l�b�g�����ŁA���ڃ��[�J�[���珤�i�������Ƃ�����A���ꂼ��̓X�̏����X���֓������B�܂ł̉^���S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A��B�ɉ����Ǝ҂���Ђ��邾���ŁA���̉����Ǝ҂���Z�Z�̏��i���܂Ƃ߂Ďd����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂ŁA�֓������B�Ԃ̉^�����S���̈�ɉ�����B��������Ǝ҂��珬���Ǝ҂ɔz�B����K�v�����邪�A���̃R�X�g�͒n��������炻��قǑ傫���Ȃ��B�]���āA��ʓI�ɏ����X�����ڃ��[�J�[����d���������A�����Ǝ҂�ʂ��������R�X�g�͉�����̂ł���B
�@�����Ǝ҂��o�R���������L���ɂȂ���̗��R�́A�o�[�Q�j���O�p���[�ł���B���悻���Ƃ̋����͂Ƃ����̂́A�����ɑ�ʂɔ����邩�Ō��܂�B�������̂��Ȃ�A��������S���������m���Ɉ����̂��B�l�b�g������s�ꋣ�������������A���m�̒l�i��������������ʂ�����͎̂��������A����Ȃ��̂Ȃǖ��ɂȂ�Ȃ����炢�A��ʍw����O��ɂ��������@���̕������ʂ�����B�c�O�Ȃ���A�l�b�g�̐��E�ł������ȏ����X�ɂ͉����Ǝ҂قǂ̗͂͂Ȃ��̂ł���B
�@�����Ǝ҂��o�R���������L���ɂȂ��O�̗��R�́A�����Ǝ҂������Ă��郊�X�N���S�@�\�ł���B�����Ǝ҂́A�P�ɉE���獶�ւƏ��i�𗬂��Ă��邾���ł͂Ȃ��B���i�����Ƃ��ɂ́A�Ⴆ�Ό������߂̗����������Ƃ����`�ŏ����X�ւ̐M�p���^���s���Ă���B�܂��A���i�ɂ���邪�A�����X�Ŕ���c�����ꍇ�A���i�̕ԕi������ɉ����Ă���鉵���Ǝ҂�����B�����Ǝ҂̂����������X�N���S�@�\�����邩�炱���A��ׂȏ����X�͈��S���ď����𑱂��邱�Ƃ��ł���̂��B
�@������Ɖ����Ǝ҂̋@�\�𗝉�����A���ꂪ�l�b�g�Ȃǂɒu����������͂����Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B�����X���C���^�[�l�b�g�ɒu���������邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�{�̖͂`���ŏq�ׂ��Ƃ���ł���B�v����ɁA���������_���̂��̂��A�r�W�l�X�𗝉����Ă��Ȃ��w�҂��������グ���ϑz�������̂ł���B
�Q�l�Q�D
�X�i��Y�w�T�����m�o�ρx�Q�O�O�P�D�W�D
�h�s�o�u���͂Ȃ���������
�@��N�O�܂ł���قǐ���オ���Ă����h�s�v���̔M�������������߂Ă��܂����B�A�����J�̃j���[�G�R�m�~�[�����[�h����ƌ���ꂽ�h�b�g�R����Ƃ����X�Ƀ��X�g����o�c�j�]�ɒǂ����܂�A�����͈�N�Ŏl���̈�ȉ��ɉ��������B�h�s�ˑ��̐����𑱂��Ă����A�����J�o�ς̌����͑����A���ォ�Ȃ蒷�����ԗ����オ�邱�Ƃ��ł��Ȃ����낤�B
�h�s�o�u���̏͂ǂ��݂Ă�1920�N��̃A�����J�Ɠ����������B��ꎟ���E���̐��ɂȂ�Ȃ������A�����J�́A�������E�̍H��Ƃ��Ă̒n�ʂ��m�ۂ��Ă����B�����ɉ�������̂��A�����Ԃƍ������H�ɂ��l�b�g���[�N�v���������B�V�����l�b�g���[�N�̓A�����J�l�̐��������{�I�ɕς��A���̒��S��i�ł��鎩���Ԃ̐��Y��Ɛ肷��A�����J�̔ɉh�͉i���ɑ����ƍl����ꂽ�B���܂ł̏펯���ʗp���Ȃ��V���Ȑ����X�e�[�W�̓j���[�E�G���i�V��������j�ƌĂ�A�����ԂƂ͊W�̂Ȃ��Ǝ�̊�Ƃ��A�Z�Z���[�^�[�X�ƎЖ���ύX�����B
�����͏㏸�𑱂��A�A�����J�l�͔ɉh�ɓ��������B�������A��O�̍D�i�C��1929�N��10��24���ɔj�ǂ��}�����B
�[�l�������[�^�[�X�̊����ɑ�ʂ̔��蒍�����������̂��\���̂��������������B�����Ċ��҂�����������ƁA�����Ԃ̐��Y�͂킸���S���̂P�ɂ܂ŋ}�������B���̌��|����Ȍi�C�̂�ꂽ�ɂ�������炸�A�����ԎY�Ƃ��O���ɏ�����̂́A��Q�����E���ŌR���p�ԗ��̎��v�������Ă��炾�����B
�����Ԃ��̂��̂����������킯�ł͂Ȃ��B�������A�o�u���̗��j���������Ƃ́A���߂�����҂̌�ɂ͒��������̎��オ�K���Ƃ������Ƃ��B
�C�M���X�Ŕ��������^�̓o�u����S���o�u����U��Ԃ��Ă݂Ă��A�ǂ����V�����l�b�g���[�N�Y�ƂƂ����̂̓o�u�����N�����₷���悤�ł���B�l�b�g���[�N�͂��̐��i����A�����̐l�X�̐���������邽�߁A�l�X�̊S���W�߂₷������ł��낤�B
�������A���Ȃ��Ƃ����{�ł́A�o�u���̌����͂��ꂾ���ł͂Ȃ��������낤�B���͍ő�̌��������x�������̐������f���������̂��Ǝv���B
���x�������̌o�c�҂́A�V���Ȑ������삪���ɂȂ�̂������ɋC���Ă���悩�����B��������ɓ������Ă���Ίm���ɗ��v��������ꂽ���炾�B�Ⴆ�A�e���r���o�ꂷ��Ƃ�������A�Ɠd���[�J�[�͊e�Ђ�����ăe���r�̐��Y���s�����B����ł��A�����������тő�ʏ�������Ă��ꂽ����A�ǂ̉�Ђ̓��������ʂɂ͂Ȃ�Ȃ������B
�Ƃ��낪���x�������I���ƁA�V�����������i�Ƃ����̂́A�قƂ�Ǔo�ꂵ�Ȃ��Ȃ����B�����������ɓ���������悢�̂��A�o�c�ҒB�͕�����Ȃ��Ȃ��Ă����B������V������������ɋQ���Ă����̂ł���B
�����ɓo�ꂵ���̂��h�s�v���_�������B��Q�̎Y�Ɗv���ƌ����A�h�s�����p�����r�W�l�X���f�����J�����邱�Ƃ�������Ƃ̔ɉh���x����ƌ���ꂽ�B�������h�s�r�W�l�X�͐��K���A�g�b�v�V�F�A�����Ȃ��ƍ����ɂ͂Ȃ�Ȃ��ƌ��`���ꂽ�B��������ɋQ���Ă����o�c�҂����ɂƔ�т��Ȃ��͂����Ȃ������̂ł���B
�������A���܂ɂȂ��Ďv���ƁA�����Ɨ��\�ȋc�_���܂���Ƃ����Ă������̂ł���B�Ⴆ���R�}�[�X�̒��������_���B�C���^�[�l�b�g�����B����ƁA���[�J�[�Ə���҂����ڌ��ѕt������A������s�������̉����Ƃ͉�ł���ƌ���ꂽ�B�������A����Ȃ��Ƃ͋N����Ȃ������B���퐶���ɕK�v�ȑ�ʐ��Y�i���l�b�g�Ŏ������邱�ƂȂǂقƂ�ǂȂ������̂ł���B��Âɍl����A����͓�����O�̂��Ƃł���B������p����ٓ����̂ɁA���������l�b�g�Œ������Ă�����肪�������Ďd���Ȃ��B�X�[�p�[��R���r�j�Ŕ��������ق��������Ƒ����ĕ֗����B����Ƀl�b�g�Œ�������ƁA���������̐U�荞�ݎ萔�����������Ă��܂��B����R�X�g���Ȃ��Ȃ�ǂ��납�A����R�X�g�����ɍ����̂��l�b�g����Ȃ̂ł���B
���[�J�[������݂�A��l��l�̏���҂ɒ��ڔ̔��Ȃǂ��Ă�����A������肪�����Ă�����Ȃ��B��������A�����Ǝ҂Ɉꊇ���ďo�ׂ��āA�������珬���X�A����҂Ə��i�𗬂����ق����͂邩�Ɍ����͍����B�����牵���Ƃ����ł��邱�ƂȂǂȂ��̂ł���B
���i���B�ł��������Ƃ�����ꂽ�B�Z�b�g���[�J�[�ɏ��i��[�������������Ǝ҂��l�b�g�s��ɔ[�����i����D����B��������Ί��S�����������āA���B�R�X�g���啝�ɉ�����Ƃ����̂��B
�m���ɃZ�b�g���[�J�[�́A�l�b�g�̉��i���J�Ƀ`�F�b�N���Ă���B���������ۂɂ͂��̌����l�Ŕ������Ƃ͂Ȃ��B�������[�^�[���Ăт��A����@���A�{����āA�M���M���̐��܂ʼn��i������������̂����B�S���҂̎d���Ȃ̂ł���B�l�b�g�͊���@������A�{������ł��Ȃ�����A���B�̒��������ł��Ȃ��̂ł���B
�܂�A�l�b�g�̓r�W�l�X�`�����X�����X�ɐ��ݏo�����@�̏�Ȃǂł͌����ĂȂ������̂ł���B
�������A���͈�����Ӗ��Ńl�b�g�͊v�����N�������낤�ƍl���Ă���B����͍��܂ł̗��ʂ̎d�g�݂ł͌����ĂȂ��邱�Ƃ̂Ȃ������l�ƌl�̎�����\�ɂȂ������Ƃł���B
�l�b�g�I�[�N�V�����̍ő��ł��郄�t�[�I�[�N�V�����̔N�ԗ��D�z��1000���~���Ă���B���̃h�b�g�R����Ƃ��s�U�ɂ������Ȃ��A�U���Ԃ̃}�j�A�����l�b�g�r�W�l�X�ő�����҂��ł���l�͐������B
�Ȃ����Â�������Ă���̂��ƌ����A�C���^�[�l�b�g�̂������ŁA����܂Ŋ|���������ň���ɐi�܂Ȃ���������҂̑��l���A���邢�͌̊m���Ƃ����̂���C�ɐi��ł�������ł͂Ȃ����낤���B
��Ƃ����鏤�i�Ƃ����̂́A���ǂ͑�ʐ��Y�i�ł���B��ʐ��Y�i�͎���R�X�g�̍����l�b�g����ɂ͌����Ȃ��B�������A��Ƃ����l����������҂̃j�[�Y�ɂ��������������邩�Ƃ������������ł���B����҂̑��l�����i�߂ΐi�ނقǁA����܂Ŋ�Ƃ��s���Ă������i�폭�ʐ��Y�Ƃ����T�O�����Ⴂ�ɗ��킷��قǁA����҂̗~��������̂��~�N���̐��E�ɕ������čs�����炾�B
�܂��A�}�j�A�Ƀ��m�낤�Ǝv�����狟���Ҏ��g���}�j�A�ɂȂ�Ȃ���A�}�j�A�̋C�����͕�����Ȃ��B��Ƃ͂�����ł��Ȃ�����A���l�������l�Ƀ}�j�A�ȏ��i�������ł���̂͌l�����Ȃ��̂��B
�l�b�g�Љ�{���ɂ����炷���̂͊�Ƃ̒����ƌl�̊m���Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
��l�̎Y�Ɗv��
�@���܃h�C�c��A�����J�𒆐S�ɁA�u��l�̎Y�Ɗv���v������Ă���B���̎Y�Ɗv���͏��C�@�ցA���̎Y�Ɗv���͓d�C�A��O�̎Y�Ɗv���̓}�C�N���G���N�g���j�N�X�A�����đ�l�̎Y�Ɗv���̓��{�b�g�Ɛl�H�m�\�ɂ����̂��B���̑�l�̎Y�Ɗv���𐧂��鍑���A���ꂩ��̐��E�o�ς𐧂���Ƃ������Ă���B
�@���݂܂ő����Ă�����O�̎Y�Ɗv���́A�l�d�i�}�C�N���G���N�g���j�N�X�j�v���Ƃ��Ă�A�m�b�H��@�B��}�V�j���O�Z���^�Ȃǂ̂e�`�i�t�@�N�g���[�I�[�g���[�V�����j�@��A���[�v���A�p�\�R���A�R�s�[�@�Ȃǂ̂n�`�i�I�t�B�X�I�[�g���[�V�����j�@�킪�A���Y���̌���ɑ傫�Ȗ������ʂ������B�����A����܂ł̑�O�̎Y�Ɗv���ł́A�@��̑������e�i���X���s�����߂ɁA�l�Ԃ��s���̑��݂������B��l�̎Y�Ɗv���ł́A�l�H�m�\����������{�b�g���A�H��S�̂��Ǘ����A�w�����o�����Ƃɂ���āA���ɂ̐��Y�����オ�����炳���B���łɁA�����������g�݂̓h�C�c�����łȂ��A���{�ł����X�Ɛi��ł���B�������A������ԋC�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ́A��l�̎Y�Ɗv�������Y�H���ւ̓K�p�Ƃ����ʂł����l�����Ă��Ȃ����Ƃ��B���͑�l�̎Y�Ɗv���̈�ԑ傫�Ȍ��ʂ́A�l�H�m�\����������{�b�g���A���i���̂��̂ɂȂ邱�Ƃ��Ǝv���B
�@���܂␢�їތ^�ň�ԑ����̂̓V���O�����т��B���̃V���O���̃p�[�g�i�[�Ƃ��āA�l�H�m�\���ڂ̃��{�b�g������悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B���łɃt�B�M���A�̑��`�Z�p�͊m�����Ă��邵�A�����V�~�����[�V�����Q�[���Ől�H�m�\�̋Z�p�����Ȃ�̃��x���ɗ��Ă���B�����ɐl�^���{�b�g�̍쓮�Z�p�������A���͐��N�ȓ��ɗ��l�^���{�b�g�̎����͉\���Ǝv���̂��B